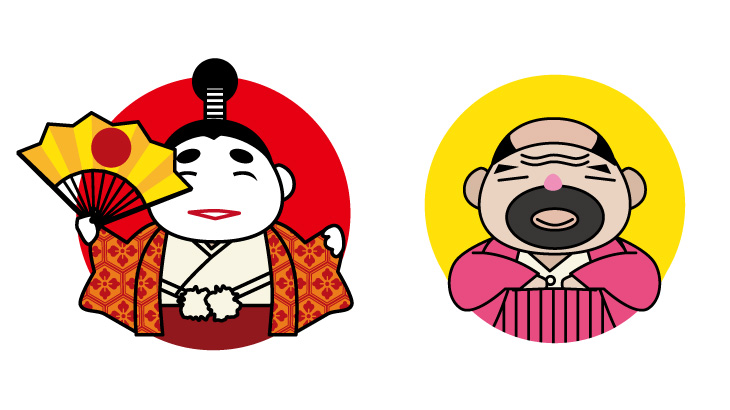先日、志村さんの一周忌を追悼したNHK総合の「プロフェッショナル仕事の流儀」という番組で「志村が最後にみた夢―コメディアン・志村けん~」と題して放映されたのを見た。
このシリーズ番組は超一流のプロフェッショナルに密着して、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリーで、NHKのレジェンド番組であった「プロジェクトX」の流れをくむ、時代の最先端で格闘している人々を見つめるという、コンテンツが好きで、筆者はよく見ることが多い番組である。
番組では、志村さんが出演したNHKのコント番組「となりのシムラ」や連続テレビ小説「エール」、生きていれば志村さんが主演を務めるはずだった映画「キネマの神様」などの関係者や志村さんをよく知る人々の証言、そしてNHKに残された秘蔵映像などから、志村さんが貫いた「笑いの流儀」と生涯をかけて目指した「夢」をひもといていた。
様々な証言がある中でも、「キネマの神様」の山田洋次監督が語っていた言葉が印象的であった。「滑稽な人間を演じることは、悲しいこと。人間の深い悲しみが良くわかっていなければ、出来ない。僕に言わせれば、最後の喜劇俳優だった」と評していた。
この番組を視聴しながら思い出したのは、志村さんが、昨年亡くなった翌月の4月に、彼の著作である「志村流-当たり前のことが出来れば仕事も人生も絶対に成功する(王様文庫)」という本が、月間ビジネス書ランキング一位となったことである。当時、まだコロナの流行し始めで、筆者もそれまでの仕事のセミナーや講演のヒントをよく探していた時期なので、毎月のビジネス書ランキングはいつも気にかけていた。志村さんの書籍が一位になったと知ったときは、読者に亡くなった追悼の気持ちが強くて売れているのだろうくらいにしか思わずに手にして読んでみて、ちょっと軽率な評価だったと恥じ入った。
正直に言ってそれまで彼について、よく考えたことがなかった。確かに彼の演ずる「バカ殿」や「変なおじさん」のコントぐらいは度々目にしていたので、ナンセンスな軽コントとして面白がってはいた。
その時、彼の著書を読んで、彼が自分のマンネリ化したギャグを音楽に例えれば「スタンダードナンバー」のようなものだと冷静に分析して、身体を動かすコントを続けてきたコメディアンとしての職人的なプライドを語っているのを読んで彼に対する認識を改めた。
テレビ番組の「志村けんのバカ殿様」は15年も続く中でも放送回数は25回だというのには驚いた。キャラクターブランドの維持には「飽きられず、忘れられず」を基本戦略として、慎重すぎるぐらいに「露出管理」を徹底していたのだ。そのマネジメント力に脱帽した。
改めて、志村けんさんを一番評価できる点はただ一つ。
彼はコント以外やらなかったことである。
今のテレビ番組を見ていてうんざりするのは、あらゆる番組がいわゆるお笑い芸人によって、仕切られてしまっているという現状である。ニュースだろうが、バラエティだろうが、旅も食事の番組も、ドラマでさえ、なんでもかんでも出てくることだ。お笑い芸人はお笑いに撤するのが、ひと昔前の芸人の矜持であった。芸人は観客をうならせる、芸をやってほしい。
人気者になれば何をやってもいいという昨今のテレビ文化は芸術家としてのけじめやプライドみたいな感覚が日本のマスコミやメディア界に欠如していると思うのは筆者ばかりであろうか。人気で売れていれば視聴率が良いという安易な選択が続けばテレビ文化に明日ないと思うのである。
トーク番組でお笑い芸人達が、お互いのプライベートを揶揄して、仲間うちで、面白がって盛り上がっているのが視聴者に受ける時代にあえて、あらがって、わかりやすいキャラクターを生かして、虚無的な空間を作り続けることが、どれだけ困難な営みで、どれだけ頑固な笑いの思想を必要としたか、「志村けん」の生き方をみて思いしらされた。
彼のコントはあきらかに今の芸人のコントとは違う。彼のコントには何かしらの仕掛けがある。決して話術や所作の笑いだけではない。視覚的で動きの大きいギャグが作られていた。
分かりやすく、丁寧なギャグであった。見る人に、気を使わせない親切なギャグである。もっと泥臭い笑いであり、生きるに必要な笑いを提供していたと思うのは褒めすぎだろうか。そういうものを作る為に、「志村けん」は全力を傾けていた。
喜劇人や役者がいなくなるたびに、人はいつかいなくなるものだったなと身につまされる。特にここ最近は味わいのある個性的な名優が次から次へと亡くなる。エノケンの後にエノケンが出ないように、渥美清の後に渥美清が生まれないように、「志村けん」のあとに誰かが代わって出てくるものではない。
我々は、時代の変遷の中で自分のスタイルを貫いた。喜劇の最後のプロを見ることが出来た。